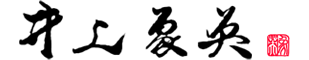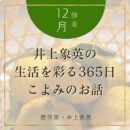「四時果てる月」とは1年の四季終わる事をさしています。昔は12月(子月)が新年でした。お正月もお盆と同じように先祖の霊を弔う月だったのです。
それでは12月のこよみをお届けいたします。
*ご案内*
日本の豊かさを知っていただきたい
足を運んでいただきたいという想いを込めて
一部の記事には関連リンクも差し込んでおります
どうぞお楽しみくださいませ
12月1日「歳末助け合い運動」のお話
年の暮れに見かける「歳末助け合い運動」ですが…

2024.11.30
年の暮れに見かける「歳末助け合い運動」ですが、いつ頃から始まったのか、知る人は少ないかも知れません。この活動は、歳末(年の瀬)に地域...
12月2日「陰暦から太陽暦へ」のお話
今日は、太陰太陽暦から太陽暦へ変わったお話を致します。

2024.11.30
年の暮れに見かける「歳末助け合い運動」ですが、いつ頃から始まったのか、知る人は少ないかも知れません。
この活動は、歳末(年の瀬...
12月3日「橘始黄(たちばなはじめてきばむ)」のお話
この頃になると、実りの秋も終盤に入り…

2024.11.30
この頃になると、実りの秋も終盤に入り、野生のあらゆる動物や植物も冬支度に入ります。
七十二候の「橘」(たちばな)は柑橘類の一種...
12月4日「忘年会」のお話
年末の恒例行事「忘年会」、意外にも恒例行事としての歴史があります。

2024.11.30
年末の恒例行事「忘年会」、意外にも恒例行事としての歴史があります。古来、年越しにご先祖様や死んだ人の御魂を祭る風習があり、平安時代の...
12月5日「納めの水天宮」のお話
全国の「水天宮」の総本山は福岡県久留米にあります。

2024.11.30
全国の「水天宮」の総本山は福岡県久留米にあります。ご祭神は天御中神と安徳天皇そしてご母堂。東京日本橋の「水天宮」は安産祈願の聖地と言...
12月6日「冬将軍」「子安神社」のお話
厳しい寒さの到来を「冬将軍」と言います。

2024.11.30
厳しい寒さの到来を「冬将軍」と言います。遠いシベリアから来る寒気団が、日本海で多くの雪を降らせる様子を擬人化した表現なのです。フラン...
12月7日「大雪(たいせつ)」のお話
今日は「大雪」。雪が降り積もり、あたり一面銀世界・・・。

2024.11.30
今日は「大雪」。雪が降り積もり、あたり一面銀世界・・・。それが「大雪」のイメージです。
今年は秋が短く暖冬かと思ったら、急に寒...
12月8日「こと納め」「納めの薬師」のお話
2月8日が「こと始め」としたところは、今日の12月8日が農事を終える区切りの日。

2024.11.30
2月8日が「こと始め」としたところは、今日の12月8日が農事を終える区切りの日。
「こと納め」になります。事とはお祭り事の意味...
12月9日「京都了徳寺大根炊き」のお話
鎌倉時代に親鸞上人様へ…

2024.11.30
鎌倉時代に親鸞上人様へ、村人達が感謝のしるしとして出したダイコンの煮つけ。
この頃、大根炊きが京都の神社仏閣での風物詩となって...
12月10日「納めの金毘羅」のお話
12月に入ると様々な神社が“納め”の時期を迎えます。

2024.11.30
12月に入ると様々な神社が“納め”の時期を迎えます。
“納め”とは今年最後の大祭を指しているのです。「こんぴらさん」の呼び名で...
12月11日「閉塞成冬(そらさむくふゆとなる)」のお話
実りの秋が終わり、あらゆる動植物が冬支度に入ります。

2024.11.30
実りの秋が終わり、あらゆる動植物が冬支度に入ります。
時代は変化しても自然の営みはいつの世も変わりません。春・夏・秋・冬と、そ...
12月12日「漢字の日」のお話
さて今年の漢字は何でしょうか?

2024.11.30
さて今年の漢字は何でしょうか?
毎年この日、京都の清水寺の貫主様が、全国から応募された漢字の中から「今年の漢字」を一字選ばれ大...
12月13日「正月こと始め」のお話
ギリギリまで溜め込まず、少しずつ始めたい正月の準備。

2024.11.30
ギリギリまで溜め込まず、少しずつ始めたい正月の準備。農耕の始まる奈良や平安時代には神様を祭って多くの神事をしていたことは考古学でも立...
12月14日「東京高輪泉岳寺義士祭」のお話
「義士祭」は4月と12月に東京高輪の泉岳寺(曹洞宗)で行われる行事です。

2024.11.30
「義士祭」は4月と12月に東京高輪の泉岳寺(曹洞宗)で行われる行事です。
とくに赤穂浪士の討ち入りの日に合わせて開催される12...
12月15日「年賀郵便特別扱い」のお話
現代では、昔の礼儀作法は通じないことが多いかも知れませんが…

2024.11.30
現代では、昔の礼儀作法は通じないことが多いかも知れませんが、今日から年賀はがきの特別取り扱いがスタートします。
新年のご挨拶状...
12月16日「食文化の習慣」のお話
お蕎麦に欠かせない唐辛子。江戸時代の内藤新宿…

2024.11.30
お蕎麦に欠かせない唐辛子。江戸時代の内藤新宿、今でいう東京の新宿区1丁目~3丁目にあたりでトウガラシが栽培されていたことを知っていま...
12月17日「東京浅草観音歳の市」のお話
東京の浅草寺では、新年に向けた縁起物や正月の必需品を売る店が…

2024.11.30
東京の浅草寺では、新年に向けた縁起物や正月の必需品を売る店が多く並ぶ「歳の市」がこの日からスタートします。
金竜山浅草寺は天台...
12月18日「鱖魚群(さけのうおむらがる)」のお話
“鱖魚”は“けつぎよ”と読みますが、一般には「鮭」のことを指します。

2024.11.30
“鱖魚”は“けつぎよ”と読みますが、一般には「鮭」のことを指します。
すさまじい数の鮭が産卵のために命をかけて河をさかのぼるこ...
12月19日「一陽来復」のお話
冬至に欠かせない「一陽来復」のお話を致しましょう。

2024.11.30
冬至に欠かせない「一陽来復」のお話を致しましょう。
日本では、太陽の恩恵に感謝して冬至祭りをします。それが「一陽来復」の神事で...
12月20日「ゆず湯」のお話
冬至の日は「ユズ湯」で無病息災祈願。

2024.11.30
冬至の日は「ユズ湯」で無病息災祈願。
全国的に知られている「ゆず湯」、温泉に入ってホッとする日本人は、遠い昔から禊祓いを生活習...
12月21日「冬至」のお話
冬至は一年で一番昼が短く、夜が長い。

2024.11.30
冬至は一年で一番昼が短く、夜が長い。
つまりこの日、北半球では最も日が短く、この日を境にして夏至までは昼所時間が徐々に長くなっ...
12月22日「納めの大師」のお話
真言密教を広め、根本道場として高野山を開いた空海は…

2024.11.30
真言密教を広め、根本道場として高野山を開いた空海は、弘法大師としても有名な方です。
今日はその大師様の命日であり、お祭りしてい...
12月23日「スス払い」のお話
この「スス払い」は、お正月に神様を迎えるために…

2024.11.30
この「スス払い」は、お正月に神様を迎えるために屋敷内のホコリヤやススを払うこと。
昔は家の中に囲炉裏があったので、「スス払い」...
12月24日「クリスマス・イブ」のお話
「クリスマス・イブ」とはキリストの生誕を祝う前夜祭のこと。

2024.11.30
「クリスマス・イブ」とはキリストの生誕を祝う前夜祭のこと。
日本では宗教的な意味合いは薄いようですが、もはや欠かす事の出来ない...
12月25日「クリスマス」「終い天神」のお話
世界中の子供達がこの日…

2024.11.30
世界中の子供達がこの日、サンタさんからのプレゼントを心待ちにしているのではないでしょうか。
キリスト教の聖人セント・ニコラウス...
12月26日「門松」「正月飾り」のお話
クリスマスが過ぎるといよいよお正月の準備です。

2024.11.30
クリスマスが過ぎるといよいよお正月の準備です。
この「門松」は近年になって出来たシステムで、元来は常緑樹なら何でも良かったので...
12月27日「官庁ご用納め」「神棚や仏壇の清め掃除」のお話
お役所や会社も年内のお仕事を終える、御用納めの頃になりました。

2024.11.30
お役所や会社も年内のお仕事を終える、御用納めの頃になりました。
年明けも気持ちよく仕事が始められるように、一年の感謝を込めて大...
12月28日「麋角解(さわしかつのおつる)」のお話
シカの角が生え変わる時期を指しています。

2024.11.30
シカの角が生え変わる時期を指しています。
日本のシカの角が生え変わるのは春から夏にかけてで、この侯でいうところのシカは「ヘラジ...
12月29日「お節料理の準備(支度)」のお話
それぞれに意味のある「おせち」料理。

2024.11.30
それぞれに意味のある「おせち」料理。本来は神様にお供えする「お節供料理」を意味するもので、五節句のたびにお供えし、頂いていたものが、...
12月30日「鏡餅」と「餅つき」のお話
歳神様の依り代となる鏡は太陽と月。

2024.11.30
歳神様の依り代となる鏡は太陽と月。「日々を重ねる」という意味の縁起の品々です。
飾り方は地方によってそれぞれですが、古来、稲に...
12月31日「年越し」「大祓い」「除夜の鐘」のお話
毎月の月末を「晦日」と言います。

2024.11.30
毎月の月末を「晦日」と言います。今日は一年の最後の日なので「大」付け、一年を締めくくる「大晦日」。1年の内に2回、6月を「夏越の祓い...