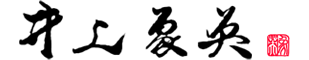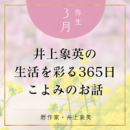衣更着(ころもを さらに かさねる)と書いて“きさらぎ”とも書きますが、衣服を重ね着するのではありません。植物が生き返ること、自然の大地の生と死との循環、「更生」と「復活再生」の息吹を意味しているのです。
それでは3月のこよみをお届けいたします。
*ご案内*
日本の豊かさを知っていただきたい
足を運んでいただきたいという想いを込めて
一部の記事には関連リンクも差し込んでおります
どうぞお楽しみくださいませ
3月1日「修二会」のお話
今日は3月1日、修二会の始まりです。東大寺の修二会の正式名称は…

2025.02.28
今日は3月1日、修二会の始まりです。東大寺の修二会の正式名称は、十一面悔過といいます。二月堂本尊の十一面観音菩薩様の方前で日々の過ち...
3月2日「草木萌動(そうもくめばえいずる)」のお話
文字のごとく1日~5日にかけて、野山の草木が生き生きと…

2025.02.28
文字のごとく1日~5日にかけて、野山の草木が生き生きと萌え始めた季節が到来したことを教えています。 冬の間、眠りについている自然界の...
3月3日「ひな祭り」のお話
祖母から母へ、そして子供へと代々受け継がれるひな人形。

2025.02.28
祖母から母へ、そして子供へと代々受け継がれるひな人形。平安時代からの宮中儀礼で、女の子の健やかな成長を願う年中行事です。もともと3月...
3月4日「ひな人形のお片付け」のお話
3月3日のひな祭りを過ぎてもお雛様を飾っていると“婚期が遅れる”と言われますが…

2025.02.28
3月3日のひな祭りを過ぎてもお雛様を飾っていると“婚期が遅れる”と言われますが、本当!!これは汚れを人形に託し川に流して厄を祓う「流...
3月5日「啓蟄」のお話
今日は、二十四節気の啓蟄となります。

2025.02.28
今日は、二十四節気の啓蟄となります。「啓」はひらく。「蟄」は虫や諸動物がこもる意味です。
つまり「啓蟄」とは、土の中にもぐって...
3月6日「気」のお話(2024年7月5日)
今日は「気」のお話をいたしましょう。

2025.02.28
今日は「気」のお話をいたしましょう。あの見えない気ですよ。人は昔から自然の働きや癒しの空間に「気」が宿ると言います。
気は地球...
3月7日「二十四節気」のお話
今日は二十四節気のお話をいたします。

2025.02.28
今日は二十四節気のお話をいたします。四季の移り変わりを分かりやすくするために、一年を四等分したのが二十四節気です。冬至と夏至、そして...
3月8日「国際婦人デー」のお話
1904年、アメリカのニューヨークで、婦人の参政権を求めたデモが起源…

2025.02.28
1904年、アメリカのニューヨークで、婦人の参政権を求めたデモが起源と言われていますが、
1917年のロシアの二月革命が発端と...
3月9日「茨城・鹿島神宮祭頭祭」のお話
今日、鹿島神宮では祭頭祭が行われます。

2025.02.28
今日、鹿島神宮では祭頭祭が行われます。茨城の鹿嶋市に鎮座する元、官幣大社の鹿島神宮は、海上保安や道案内の神様として信仰されています。...
3月10日「塩竃神社帆手祭り」のお話
宮城県の塩竃市にある海の神…

2025.02.28
宮城県の塩竃市にある海の神・塩土老翁神をご祭神としている奥州一之宮塩竃神社は、平安時代の創建とされています。塩竃とは、海の水から塩を...
3月11日「桃始笑(ももはじめてさく)」のお話
中国では長寿のシンボルとされる桃。

2025.02.28
中国では長寿のシンボルとされる桃。見渡すかぎりの野山に濃淡のモモの花が咲き始めるころとなります。「桃源郷」と呼ぶにふさわしい景色を表...
3月12日「奈良東大寺二月堂お水取り」のお話
3月1日から始まっている修二会の行事は今日がクライマックスです。

2025.02.28
3月1日から始まっている修二会の行事は今日がクライマックスです。
“水は命を養う糧”であるとして、お堂(二月堂)の前の若狭井で...
3月13日「奈良春日大社祭」のお話
山や川、海、森、木、岩など地球の大地、万物に宿る自然の神々。

2025.02.28
山や川、海、森、木、岩など地球の大地、万物に宿る自然の神々。その神様はお祭りの時、何処からかやってきて依り代に憑依し、祭祀が終わった...
3月14日「ホワイトデー」のお話
イベント好きな国民性が作り上げた記念日。

2025.02.28
イベント好きな国民性が作り上げた記念日。バレンタインデーに対するお返しをする日として、福岡のケーキ屋さんが始めたのがきっかけのイベン...
3月15日「摘み草(野草)」のお話
“摘み草”という言葉は死語になりつつある現代…

2025.02.28
“摘み草”という言葉は死語になりつつある現代、「野草」は野の草と書きますので、これを摘むことは危険が伴いそうです。都会ではその習慣が...
3月16日「山神様」のお話
東北地方に多いお祭りですが、神様の姿は誰も見たことはありません。

2025.02.28
東北地方に多いお祭りですが、神様の姿は誰も見たことはありません。見えない・・と言った方が良いかも知れませんね。自然への感謝の思いが、...
3月17日「彼岸入り」のお話
「春分」の日をお中日として、その前後それぞれ3日、計7日間を「春の彼岸」と言います。

2025.02.28
「春分」の日をお中日として、その前後それぞれ3日、計7日間を「春の彼岸」と言います。
初めの日を「彼岸入り」とし、最後の日が「...
3月18日「石川・気多大社おいで祭り」のお話
この「おいで祭り」は、朝廷に厚遇を受けていた能登一之宮・気多大社で…

2025.02.28
この「おいで祭り」は、朝廷に厚遇を受けていた能登一之宮・気多大社で、北陸地方の守護社でもあります。 加賀藩が守護した本殿のご祭神は、...
3月19日「社日」のお話
明日は「社日」です。

2025.02.28
明日は「社日」です。「社日」は暦の歴注で、曜日の吉凶や日取りとは直接関係がありません。しかし昔から、四季に移動して私たちの暮らしを見...
3月20日「春分の日」のお話
今日は二十四節気の「春分」です。

2025.02.28
今日は二十四節気の「春分」です。昭和23年から、自然をたたえ、生き物をいつくしむ日として祝日になりました。 秋分にもあるように、この...
3月21日「雀始巣(すすめはじめてすくう)」のお話
スズメが空を飛び回り、初めて巣づくりを始める季節になります。

2025.02.28
スズメが空を飛び回り、初めて巣づくりを始める季節になります。葦原や竹やぶに多く生息するスズメは、「スズメのお宿」や「舌きりスズメ」な...
3月22日「奈良法隆寺会式」のお話
今日は3月22日、奈良法隆寺の会式の日に当たります。

2025.02.28
今日は3月22日、奈良法隆寺の会式の日に当たります。今日から24日まで奈良・斑鳩の法隆寺で聖徳太子の命日法要、会式が開催されます。法...
3月23日「ぼた餅とおはぎ」のお話
今日23日は「彼岸明け」です。

2025.02.28
今日23日は「彼岸明け」です。このお彼岸に頂く「ぼた餅」と「おはぎ」ですが、決まって春と秋に同じ風情のあんこ餅団子が出回ります。
...
3月24日「衣替え」のお話
季節の装いに敏感な日本の人々。

2025.02.28
季節の装いに敏感な日本の人々。自然と共に暮らしていた昔の良い習慣を、現代にまでつないでいる習慣。それが「衣替え」です。衣服を冬物から...
3月25日「奈良薬師寺花会式」のお話
世界遺産の薬師寺は、法相宗の大本山。

2025.02.28
世界遺産の薬師寺は、法相宗の大本山。白鳳時代(680年)ごろ、天武天皇が皇后さま、後の持統天皇の病気平癒のために建立された祈願寺です...
3月26日「なたね梅雨」のお話
本来梅雨は6月ごろとしますが…

2025.02.28
本来梅雨は6月ごろとしますが、アブラナ科の菜の花の咲くころ、休んでいた畑や里山一面に菜の花が一面に咲き広がる光景は、春の神様が微笑ん...
3月27日「利休忌」のお話
今日は「利休忌」です。

2025.02.28
今日は「利休忌」です。お茶の歴史はかなり古く、室町時代には“だんご茶”の名前で中国から漢方薬としてありました。
千利休は安土桃...
3月28日「朔」のお話
毎月、暦の中に「朔」という字が出て来ます。

2025.02.28
毎月、暦の中に「朔」という字が出て来ます。
「朔」は太陰太陽暦(旧暦)における一日のことです。月が太陽と並んで見えなくなるこの...
3月29日「桜餅と草餅」のお話
春の香りが楽しめる甘いおやつ、桜餅のお話です。

2025.02.28
春の香りが楽しめる甘いおやつ、桜餅のお話です。柏餅をまねて作ったとされる桜餅。
この桜餅は、江戸時代、桜の名所、向島の長命寺前...
3月30日「山遊び」のお話
自然が織りなす四季は一年の循環ですが…

2025.02.28
自然が織りなす四季は一年の循環ですが、人間は大自然の全てから恵みを受けて生きています。神様を迎えに行く風習の山遊びは、田植えの始まる...
3月31日「年度末」のお話
今日は年度末です。

2025.02.28
今日は年度末です。暦の上で一年の始まりは1月1日、終わりは12月31日ですが、日本においては、学校や会計年度などは、4月1日を年度始...