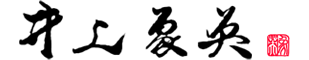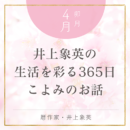卯の花が美しい時期です。温かい日が眩しく感じるころに小雨が降る時がありますが、恵みの雨は新緑を更に引き立たせます。空に虹がかかればもっと幸せに。
それでは4月のこよみをお届けいたします。
*ご案内*
日本の豊かさを知っていただきたい
足を運んでいただきたいという想いを込めて
一部の記事には関連リンクも差し込んでおります
どうぞお楽しみくださいませ
4月1日|雷乃発生(かみなりすなわちこえをはっす)のお話
春雷は春の訪れを告げる自然現象。農家にとっては虫出しの雷として野焼き準備の目安ともされる。

2025.03.31
本格的な春のおとずれを告げる空の声を指します。春に鳴る雷の音を「春雷」と言います。時には激しい雨をともなう夏の雷や稲妻とは違い、その...
4月2日|新学年のお話
4月は新学年・新生活の始まり。新しい環境での出会いや成長の機会が広がる時期。

2025.03.31
4月は新学年もスタートです。学生の方々は 新しい環境の中で、新しいお友達や仲間を作る機会、出会いのチャンスに恵まれるかも知れませんね...
4月3日|新年度のお話
日本の新年度は4月始まりが多く、会計・予算などの区切りとして重要な時期。

2025.03.31
「新年度」とは、官公庁や学校の一年の区切りを指しています。つまり、会計年度など一年を特定の時期に区切って新しい年度を迎えるのです。日...
4月4日|清明のお話
自然が清らかで生き生きとする時期。神社では春季大祭なども行われる。

2025.03.31
今日は二十四節気の「清明」です。清明とは、自然の全てのモノが清らかで生き生きとした状態をさす「清浄明潔」、つまり、「清浄」と「明潔」...
4月5日|家神様のお話
家の中にも神様が宿り、清潔を保つことが吉運を呼び込むとされている。

2025.03.31
神様は神社だけでなく、家の中のいろんな所に居て暮らしを見守っています。門の神は家に災いが寄らないように、台所には竈の火神や三宝荒神。...
4月6日|春の全国交通安全運動のお話
今日から交通安全運動週間。ドライバーだけでなく歩行者も意識向上を。

2025.03.31
今日から15日まで春の全国交通安全運動の週間です。広く国民に交通安全の思想の普及と、あらためて交通安全への意識を高めてほしい・・・と...
4月7日|世界保健デーのお話
WHOによる健康意識啓発の日。SDGsとも関わりがあり、世界の保健を考える契機。

2025.03.31
今日はWHO 世界保健機構が後援する世界規模の健康に関する啓蒙の日「世界保健デー」です。世界保健憲章は1948年の4月7日に設立され...
4月8日|花まつり(灌仏会)のお話
お釈迦様の誕生日を祝う仏教行事。誕生仏に甘茶を注いで無病息災を祈る。

2025.03.31
「灌仏会」「仏生会」はお釈迦様のお誕生日を祝う会です。別称は「花まつり」と言った方がなじみがあるでしょうか。仏教の開祖であるお釈迦(...
4月9日|長浜曳山祭のお話
ユネスコ無形文化遺産にも登録された滋賀・長浜の伝統的な春祭り。

2025.03.31
滋賀県琵琶湖の東北に位置する長浜の八幡神社の祭礼は、今日から17日まであります。
町内全体で繰り広げられる多彩な行事、動く美術...
4月10日|鴻雁北(こうがんかえる)のお話
冬鳥の雁が北へ帰る時期。春と冬の鳥の交替が季節の移ろいを示す。

2025.03.31
「鴻雁」の「鴻」(おおとり)は、大きな水鳥のことを指しています。中でも「雁」は子育てをするために、繁殖地の北の方へ旅立つ冬鳥の代表と...
4月11日|物忌みの山籠もりのお話
田植え前の祈願行事。若者が山に籠って神聖な枝を持ち帰る風習。

2025.03.31
「鴻雁」の「鴻」(おおとり)は、大きな水鳥のことを指しています。中でも「雁」は子育てをするために、繁殖地の北の方へ旅立つ冬鳥の代表と...
4月12日|大津日吉大社三王祭のお話
日吉大社で行われる比叡山の守護神の大祭。壮大な神事が4日間続く。

2025.03.31
滋賀県大津市の坂本にある日吉大社は比叡山延暦寺の東麓に位置し、京都御所の鬼門封じとして本宮を構えています。別称「山王権見」と言われ、...
4月13日|虚空像菩薩十三詣のお話
13歳の知恵を願う参拝行事。関西を中心に広まった伝統的風習。

2025.03.31
数え年13歳になった子供に知恵を授かるようにと願う親心から始まった「十三詣り」。 虚空蔵菩薩様は「知恵と福徳」の仏様です。数え年の1...
4月14日|奈良の大仏のお話
東大寺の廬舎那仏は奈良の象徴。聖武天皇の発願で建立された。

2025.03.31
今日は奈良の大仏様のお話です。皆様も修学旅行で行かれた記憶があるかと思いますが、ご存じの東大寺は華厳宗の総本山。通称「奈良の大仏様」...
4月15日|虹始見(にじはじめてあらわる)のお話
にわか雨のあと現れる虹は吉兆。古来より希望の象徴とされる。

2025.03.31
“虹は吉兆のしるし”とは皆様もご存じでしょうが、にわか雨のあとの美しい虹。時代に関係なく、空に浮かんでは消えていたのでしょう。
...
4月16日|牡丹祭りのお話
大輪の牡丹が咲く季節。奈良・長谷寺などで祭りが行われる。

2025.03.31
今頃は 大輪の牡丹の花が咲き誇るころです。牡丹は中国原産ですが、日本では観賞用として品種改良を重ねられ、大きく色鮮やかで、見事な「富...
4月17日|春の土用のお話
立夏前の18日間は「土を動かすのを避ける」土用期間とされる。

2025.03.31
“虹は吉兆のしるし”とは皆様もご存じでしょうが、にわか雨のあとの美しい虹。時代に関係なく、空に浮かんでは消えていたのでしょう。
...
4月18日|発明の日のお話
明治時代に特許制度が始まった日。創造や技術革新の大切さを学ぶ。

2025.03.31
何をもって発明の日?なのでしょう。
新しい機械や様々な道具、技術やアイデアなど、新しい方法も発明や発見になりますが、実は現在の...
4月19日|水口祭りのお話
田んぼの水口に花や枝を供えて豊作祈願を行う地域の伝統行事。

2025.03.31
この頃、苗代を整理した田んぼの水を引く口に土をもって季節の花あるいは枝やお札を御幣を刺して一年の豊作祈願をするお祭りの習慣が残ってい...
4月20日|穀雨のお話
春雨が百穀を潤すとされる節気。種まきや農作業に最適な時期。

2025.03.31
二十四節気の「穀雨」になります。月の満ち欠けで1ヶ月を決めていた旧歴では1年を24分割して太陽年の長さと合わせ、それぞれ季節にふさわ...
4月21日|葭始生(あしはじめてしょうず)のお話
水辺に葦が芽吹く頃。日本文化に根付いた植物で生活にも密着。

2025.03.31
五穀豊穣の証といわれる「アシ」が芽吹くこのころ。水辺のアシ(葭・葦)が新芽を出す季節となります。
日本神話にもその存在が明記さ...
4月22日|靖国神社春祭のお話
戦没者を慰霊する春の例大祭。政治や歴史に関わる意義深い行事。

2025.03.31
今日は東京の九段にある靖国神社の春季例大祭です。実は靖国神社は別格官幣社なのです。国の為に殉死した方々の御魂を祀る為に明治2年「招魂...
4月23日|藤まつりと潮干狩りのお話
藤の花と潮干狩りの季節。旬のアサリは料理にも最適。

2025.03.31
藤棚の下に腰掛けて空を見上げると、艶やかな花が天から降り注いで落ちて来そうです。
自分は、あのヤドリギ的成長過程で我慢強く粘り...
4月24日|フキとヨモギ、新玉ねぎのお話
春の山菜が旬。邪気を祓う植物や春の味覚を楽しむ季節。

2025.03.31
最近は、ヨモギが生えている風景も昔ほどは見かけなくなりましたが、邪気をはらう植物とされ、春のお供えには欠かすことが出来ない食材でした...
4月25日|甲子(きのえね)のお話
干支の起点となる「甲子の日」。吉日として古くから重視された。

2025.03.31
今日は甲子の日。甲子は干支の組み合わせ。
「十干」の甲・乙・丙・丁・戊・己・庚・辛・壬・癸と「十二支」の子・丑・寅・卯・辰・巳...
4月26日|霜止出苗(しもやみてなえいずる)のお話
霜が終わり苗が育つ頃。農作業や庭仕事が本格化する時期。

2025.03.31
「八十八夜の別れ霜」と言われるように、「終霜日」(終わり霜の日)も近い頃です。
昔はみるみる成長し、野山は見渡すかぎり新緑の海...
4月27日|和歌山道成寺会式のお話
安珍清姫伝説でも有名な道成寺の歴史ある行事。仏教文化が色濃い。

2025.03.31
今日は和歌山の道成寺のお話です。正式名称は天音山道成寺ですね。
大宝元年に創建された和歌山県では最古のお寺で聖武天皇の時代等か...
4月28日|苗代のお話
田植え準備の苗代づくり。昔ながらの稲作文化が息づく行事。

2025.03.31
農作業が機械化される以前では、個々の農家が苗代を作って育ててました。直播きだった稲作も、奈良時代から苗代でイネを育ててから水田に植え...
4月29日|昭和の日のお話
昭和天皇の誕生日。激動の昭和時代を顧みる国民の祝日。

2025.03.31
今日は昭和天皇の誕生日です。国が定めた国民の祝日なのです。
国民の祝日に関する法律には「激動の日々を経て、復興を遂げた昭和の時...
4月30日|佐賀有田陶器市のお話
陶磁器の町・有田での陶器市。日本の陶芸文化を体感できる名イベント。

2025.03.31
今日から5月5日まで、有田で陶器市が開催されています。有田は400年以上の陶器の歴史をもつ陶器の町。
昔、中国や朝鮮から渡来し...