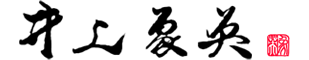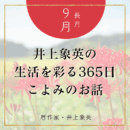夏は夜が短かったので、この月に入ると急に夜が長く感じます。そしてこの頃、五月と同じように長雨の降る時があります。カビが生えやすくなるので換気や風通しはマメに致しましょう。それでは「9月のこよみ」をお送りいたします。
*ご案内*
日本の豊かさを知っていただきたい
足を運んでいただきたいという想いを込めて
一部の記事には関連リンクも差し込んでおります
どうぞお楽しみくださいませ
9月1日「関東大震災記念日」のお話
1923年(大正12年)9月1日。午前11時58分。

2024.08.31
1923年(大正12年)9月1日。午前11時58分に、相模トラフを震源とした地震災害が起きたのです。
地震の規模はマグニチュー...
9月2日「風の盆」のお話
雑節の二百十日も二百二十日も農家にとっては厄日と言われています。

2024.08.31
雑節の二百十日も二百二十日も農家にとっては厄日と言われています。地方では、村の境に締め縄を張って風の悪霊が入らないように願いました。...
9月3日「禾乃登(かすなわちみのる)」のお話|七十二候:処暑末候
「禾」はカ、いね、のぎとも読みます。漢字の「のぎ偏」にあるように穀類の総称です。

2024.08.31
「禾」はカ、いね、のぎとも読みます。漢字の「のぎ偏」にあるように穀類の総称です。穂が出ている穀物を指しますので、多くは「稲」の意味を...
9月4日「稲架(はさ)」のお話
稲刈りの後には欠かせない「稲架」(はさ)。

2024.08.31
稲刈りの後には欠かせない「稲架」(はさ)。とうか、稲木、稲掛けなどとも言います。クイを交差させて丸太を渡したところに刈り取った稲を束...
9月5日「ミョウガ」のお話
そろそろ旬も終わりのころです。

2024.08.31
そろそろ旬も終わりのころです。ショウガ科の「ミョウガ」は、若い花穂が特別に香りがよく、日本では平安時代から抗菌作用のある重要な野菜と...
9月6日「社日」「小つち」のお話
「社日」も「小つち」も土地の神様です。

2024.08.31
「社日」も「小つち」も土地の神様です。秋の社日は「秋社」とも呼ばれ、秋分の日に最も戊(つちのえ)の日。この日は五穀の神を祀ってお豊穣...
9月7日「白露(はくろ)」のお話
「陰気ようやく重なりて 露凝りて 白色となればなり」

2024.08.31
「陰気ようやく重なりて 露凝りて 白色となればなり」と・・・キラキラと輝く草露が目に浮かぶ、情緒的で美しい詩ですね。
秋分から...
9月8日「草露白(そうろしろし)」のお話
この時期、野山を散策すると足元がしっとり濡れていることがあります。

2024.08.31
この時期、野山を散策すると足元がしっとり濡れていることがあります。「草露」(そうろ)と、はまさしく“つゆくさ”のこと。空気中の水蒸気...
9月9日「重陽の節句」のお話
「重陽」は五節句の一つ。

2024.08.31
「重陽」は五節句の一つ。中国の陰陽思想から奇数は縁起の良い数字で、とくに9は陽数の最も大きい数。
その9が二重に重なるので「重...
9月10日「二百二十日」のお話
明暦2年に『伊勢暦』に初めて登場する「二百十日」という言葉は大変有名です。

2024.08.31
明暦2年に『伊勢暦』に初めて登場する「二百十日」という言葉は大変有名です。しかし皆様は「二百二十日」は聞き慣れないかもしれませんね。...
9月11日「秋の長雨 秋霖(しゅうりん)」のお話
9月の中旬頃から一か月あまり、梅雨のように雨が降り続く時期…

2024.08.31
9月の中旬頃から一か月あまり、梅雨のように雨が降り続く時期を、秋の長雨と呼んでいます。
「秋霖」(しゅうりん)とも言われ、南の...
9月12日「彼岸の準備」のお話
自分の家のご先祖様はどんな人だったのかな?と考えたことがありますか。

2024.08.31
自分の家のご先祖様はどんな人だったのかな?と考えたことがありますか。
お婆ちゃんやお母さんと“おはぎ”作りを手伝いながら、お墓...
9月13日「鶺鴒鳴(せきれいなく)」のお話
日本では「鶺鴒」(せきれい)が鳴く時期となります。

2024.08.31
日本では「鶺鴒」(せきれい)が鳴く時期となります。日本書記にも記述がある渡り鳥ですが、細い足でチョコチョコ歩き回り、谷川のせせらぎで...
9月14日「秋の七草」のお話
春の七草は七草粥にして食して滋養になりますが、秋の七草は普遍的な美しさを見て楽しむ草花となります。

2024.08.31
春の七草は七草粥にして食して滋養になりますが、秋の七草は普遍的な美しさを見て楽しむ草花となります。つまり、観賞することに意義があるの...
9月15日「老人の日・老人週間」のお話
今年の「敬老の日」は16日です。

2024.08.31
今年の「敬老の日」は15日です。一体何歳から老人になるのかしら?
年齢からすると自分はすでに老人ですが、気分は四十歳?1951...
9月16日「鎌倉鶴岡八幡宮 流鏑馬」のお話
例大祭で行われる伝統行事の流鏑馬。

2024.08.31
例大祭で行われる伝統行事の流鏑馬。神奈川県・鎌倉の鶴岡八幡宮。源の頼義が京都の石清水八幡宮のご分霊を鎌倉の由比ガ浜の地に勧請したのが...
9月17日「厄年」のお話
何歳になっても無病息災で人生を送ってゆきたいものですが…

2024.08.31
何歳になっても無病息災で人生を送ってゆきたいものですが、厄の起源は中国の陰陽道からで、日本でも平安時代から信じられてきました。「厄年...
9月18日「放生会(ほうじょうえ)」のお話
「放生会」は仏教の教えから始まり…

2024.08.31
「放生会」は仏教の教えから始まり、捕らえられた魚や鳥獣を、生きたまま池や野に放ち、日頃の殺生を悔い改める、“殺生を忌む”仏教の儀式。...
9月19日「玄鳥帰(つばめさる)」のお話|七十二候:白露末候
ちょうど9月18日〜22日ころを指した七十二候。

2024.08.31
ちょうど9月18日〜22日ころを指した七十二候。「玄鳥」(くろいとり)と書きますが、これはツバメのこと。
秋が深まり、寒さを感...
9月20日「秋の彼岸入り」のお話
「暑さ寒さも彼岸まで」の通り大分涼しくなります。

2024.08.31
「暑さ寒さも彼岸まで」の通り大分涼しくなります。秋分の日と、その前後の3日間を含んだ一週間が秋の彼岸です。その初日が「彼岸入り」と言...
9月21日「佑気とり」のお話
毎日のルーティンワークで頭がぼーっとしてしまうことがあったら…

2024.08.31
毎日のルーティンワークで頭がぼーっとしてしまうことがあったら、少しの時間でもストレス解消を考えますよね。そんな時にぜひトライしてもら...
9月22日「八朔(はっさく)」のお話
「八朔(はっさく)」と言えば、くだもののこと…と思われるでしょうが…

2024.08.31
「八朔(はっさく)」と言えば、くだもののこと…と思われるでしょうが、ここでは旧暦の8月1日。8月の“朔日”のことを指しています。つま...
9月23日「秋分の日」のお話
秋を二分する頃。暦に初秋や晩秋があれば当然、仲秋(十五夜)もあり…

2024.08.31
秋を二分する頃。暦に初秋や晩秋があれば当然、仲秋(十五夜)もあり、お彼岸のお中日です。太陽が真東から出て、真西に沈み、昼と夜の長さが...
9月24日「結核予防週間」のお話
厚生労働省では、毎年9月24日から30日まで…

2024.08.31
厚生労働省では、毎年9月24日から30日までを「結核予防週間」と定めており、これは結核予防に関する正しい知識の普及と啓発を図ることを...
9月25日「雷乃収声(かみなりすなわちこえをおさむ)」のお話|七十二候:秋分初候
あれほど活発に鳴り響いていた夏の雷もすっかり収まって、聞こえなくなる頃です。
9月26日「彼岸蕎麦」のお話
季節の変わり目で体調を崩しやすいお彼岸明けのころ…

2024.08.31
季節の変わり目で体調を崩しやすいお彼岸明けのころ、この時期、消化が良く、胃腸にも優しい蕎麦を食べて、体調を整える習慣があったと言われ...
9月27日「秋の大掃除」のお話
季節は秋の長雨の真っ最中かも知れません。

2024.08.31
季節は秋の長雨の真っ最中かも知れません。時間のある時にちょこちょこと、家の中の隅々に溜まったホコリを払う掃除をしましょう。湿気と乾燥...
9月28日「秋の食材」のお話
秋の食材は滋養に恵まれ栄養価の高い品々が多いのが特徴です。

2024.08.31
秋の食材は滋養に恵まれ栄養価の高い品々が多いのが特徴です。 栗、クルミ、ぶどう、ナシ、カボチャ、そして鮭やサンマ、秋サバとか・・・種...
9月29日「蟄虫坏戸(むしかくれてとをふさぐ)」のお話
様々な虫たちが樹木の隙間や穴、土の中に入って冬支度をするころです。

2024.08.31
様々な虫たちが樹木の隙間や穴、土の中に入って冬支度をするころです。
啓蟄初侯の「蟄虫啓戸」(すごもりむしとをひらく)で、戸を開...
9月30日「秋ナス」のお話
最近は長ナス、京ナス、水ナス、米ナス、そして白ナスなどなど…

2024.08.31
最近は長ナス、京ナス、水ナス、米ナス、そして白ナスなどなど、店頭に並ぶナスの種類が豊富になってきました。国産ナスの消費拡大キャンペー...