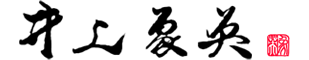【象英だより】2021年11月の活動報告と新月と満月のお話

新月と満月のお話
つい先日「月食」がありましたね。今回は新月と満月の話を致しましょう。
明治の改暦で新暦が出来るまで、長い間、旧暦(太陰太陽暦)を使っていました。幼い頃から暦の言葉になじみ、日本では縁起を担ぐ習慣も根付いていたと思います。 旧暦は、見上げた空にある月の満ち欠けを基準にして、月日を数えました。
月が見えない新月(朔=さく)から1日、2日、3日と数えて次の新月の前日までを1カ月としました。「朔」は“ついたち”とも読み、「月がたつ」意味と考えられています。一方、新月から約15日目の月が「望」。満月のことです。だから十五夜ともいいます。月の「朔望」は新月から次の新月に移るまで、または満月から次の満月になるまでにかかる時間をいいます。
平均では29日6時間ぐらいです。このように「朔望」の周期が29日と少しなので、時々は30日として1日追加する必要がありました。これが「大小暦」といわれた由縁です。旧暦の月の「大(30日)」「小(29日)」の組み合わせは年によって変わります。お手元の「象英暦」などをチェックしてみてください。
しかし、この数え方では1年は354日。正確には日数が足りません。そこで、太陽暦とのずれを合わせるために3~4年に1度「閏月(うるうづき)」を置き、二十四節気を定めて、ずれの調整をすることにしています。
農林漁業や観光業などに関係する人々はこの「太陰太陽暦」を便利に使っています。特に漁業は月と太陽の張力現象から潮の干満が気になるところ。大潮は「朔望潮」とも言われ、その力ははかり知れません。満月や大潮の時にお産が多く、新月や引き潮では人が亡くなる時間帯と重なると昔から言いました。
発生する海の自然現象を“神様の大きなため息”と考え、船を出すことも控えたのです。
先人の知恵は科学を越えていたかも知れません。
![]()